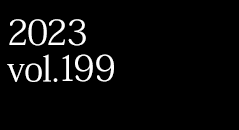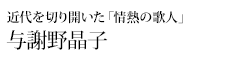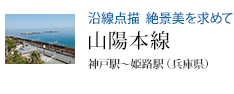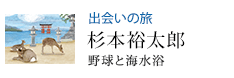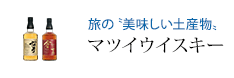その鮮やかな美しさから、海外でも「ジャパンブルー」として親しまれている藍染。植物染料の「藍」を使った染色技法には、発酵の力が大きな役割を果たす。国産ジーンズ誕生の地、瀬戸内海を臨む岡山県倉敷市児島に、今も昔ながらの手仕事で染めつける藍染職人を訪ねた。

児島駅を降りると、ジーンズの暖簾が出迎えてくれる。街にはジーンズ店の看板があちこちに見受けられる。


大正時代築の母屋の土間を利用した、高城染工場のギャラリー。当時から使用されていた家具と、濃さも柄もさまざまな藍染の暖簾が調和する。

タデ藍の葉。染料に使用されるのは葉の部分。生薬として解毒や解熱などにも用いられる。

藍の葉を発酵させて作った、徳島産の (すくも)。国産の藍だけでなく、現在は天然藍であるインド藍も使われる。
(すくも)。国産の藍だけでなく、現在は天然藍であるインド藍も使われる。

作業場に埋め込まれた備前焼の藍甕の中で3カ月かけて藍を発酵させる。藍甕それぞれ濃度が違う。


 に灰汁(あく)や小麦の皮などを入れ撹拌させて発酵を促し、還元状態の染液を作る。攪拌すると、森の中の草のような香りが立ち込め、元気な藍の華が浮きあがる。
に灰汁(あく)や小麦の皮などを入れ撹拌させて発酵を促し、還元状態の染液を作る。攪拌すると、森の中の草のような香りが立ち込め、元気な藍の華が浮きあがる。

染液に入れた布は、手で揉み込むようにして藍を染み込ませ、しっかりと絞る。

絞った布を水で揉むと、水中の酸素が反応し藍色が定着する。水は塩素の入っていない高梁川の水を使用。

絞り藍染めした麻布。ゴムや紐で縛った部分は水に浸しても色移りしない。濃淡が鮮やかに発色する。
天然藍は、世界中で最も古くから用いられてきた植物染料といわれる。西アジアでは紀元前6000年頃から使われていたとされ、紀元前3000年頃のインダス文明の遺跡からは藍染の染織槽跡が発見されている。古代エジプトのツタンカーメンのミイラにも藍染の布が使用されていたという。藍染には、「インジカン※」を主成分とする植物が使われるが、その種類は多く、熱帯地域から寒冷な地域まで広範囲に分布する。世界的にはインド藍が有名だが、日本はタデ科のタデ藍が主流である。
中国、朝鮮半島を経て、日本に藍染の技法が伝来したのは飛鳥から奈良時代とされるが、『魏志倭人伝』によると、243年に、倭国(日本)から青に染めた絹織物が魏王に献上されたと記される。奈良時代には、その貴重性から藍の栽培や藍染は「織部司[おりべのつかさ]」の所管となり、鎌倉時代後期からは藍染の専門職の「紺屋[こんや]」「紺 [こんかき]」が各地に出現し、庶民の生活へと根付いていった。木綿の普及も相まって、防虫効果のある藍は、自家用の縞[しま]や絣[かすり]の糸染めにも使われ、野良着や足袋など仕事着として庶民に愛用された。
[こんかき]」が各地に出現し、庶民の生活へと根付いていった。木綿の普及も相まって、防虫効果のある藍は、自家用の縞[しま]や絣[かすり]の糸染めにも使われ、野良着や足袋など仕事着として庶民に愛用された。
明治初めに来日したイギリス人化学者、ロバート・ウィリアム・アトキンソンは、街で目にする暖簾や庶民たちが着ていた藍染を「ジャパンブルー」と呼んで称賛した。
- ※タデ科植物の藍は、葉の部分に青色の原料となる化学物質「インジカン」を含有する。

独創的な藍染を手掛ける高城染工場4代目の角南浩彦さんと、妻の真由子さん。

元倉庫を改装したショップギャラリー。日本人の体型に合うシンプルなフォルムの服が年齢問わず支持されている。

好みの藍色が見つかるようにと、濃淡さまざまな藍染を用意。染め直しにも応じる。
岡山県南部の繊維の街、倉敷市児島。ここに1915(大正4)年創業の高城染工場がある。4代目を継ぐ角南[すなみ]浩彦さんは、現在も手作業で独自の藍染を追求している。
藍染の行程はまず、刈り取ったタデ藍の葉を乾燥させて寝かせ、水をかけて自然発酵させた「 [すくも]」と呼ばれる染色素材を作る。しかし、この
[すくも]」と呼ばれる染色素材を作る。しかし、この だけでは染まらない。ここからが角南さんの仕事となる。藍の色素(インジゴ)は不溶性のため、水溶性にするために消石灰や小麦の皮など自然の素材を加えて攪拌し、さらに発酵を促すと酸素のない状態の染液ができる。この一連の作業を「藍を建てる」といい、藍甕[あいがめ]で発酵を促し成熟させる。発酵状態を見分けるのは、表面に浮かぶ泡「藍の華」。藍の華の泡立ちが良ければ染液に栄養と力がある証だ。水に浸した布を空気に触れさせると(酸化)、布はたちまち鮮やかな藍色に変色する。マジックを見るような一瞬の変化に感動さえ覚える。
だけでは染まらない。ここからが角南さんの仕事となる。藍の色素(インジゴ)は不溶性のため、水溶性にするために消石灰や小麦の皮など自然の素材を加えて攪拌し、さらに発酵を促すと酸素のない状態の染液ができる。この一連の作業を「藍を建てる」といい、藍甕[あいがめ]で発酵を促し成熟させる。発酵状態を見分けるのは、表面に浮かぶ泡「藍の華」。藍の華の泡立ちが良ければ染液に栄養と力がある証だ。水に浸した布を空気に触れさせると(酸化)、布はたちまち鮮やかな藍色に変色する。マジックを見るような一瞬の変化に感動さえ覚える。
高城染工場のオリジナルブランド「blue in green」の服は、自社で藍染した糸を岡山県井原市で織り上げ、パターンも縫製も角南さんが手掛ける。「藍染は野良着で広まったもの。形や生地感にこだわりながら、これからも素朴な藍を生かした商品を作っていきたい」と語る角南さん。白い布に染め付けているのは藍の色であり、藍の生命力と息遣いなのかもしれない。